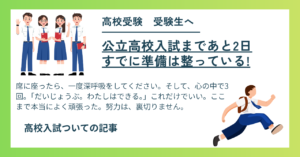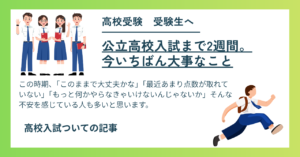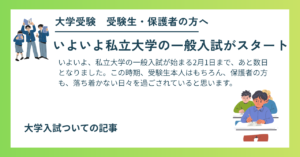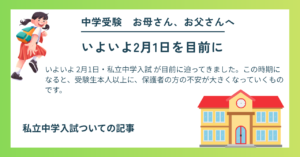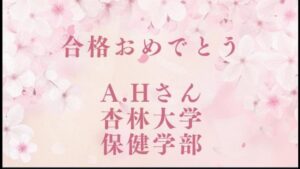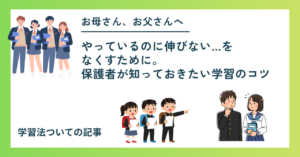大学入試に向けてのプランニングは「逆算式」で

大学入試は個々に目標が違います。高校入試のように難易度の高い高校から低い高校まで同一の問題を解くのと違い、目標によって入試科目も難易度もまったく違うのです。ですから、合格に向けての学習プランニングは個々に違うといえます。
そのプランニングは「逆算」してつくるのが基本です。
つまり入試から逆算して「いま」の位置を確認し、そこから計画を立てていくのです。全体のプランもですが、各教科ごとのプランも同じです。入試から逆算して、いま、どこまで学習が進んでいるのか、どこまで理解をしているのか、それをしっかりと確認して計画を立てる必要があります。
ステップ1 志望校を決める
志望校を決めるとは「受験に必要な科目が決まる」「受検に合格するためのレベルが決まる」ということです。ここが決まらないと計画は何も立てられません。そして、科目とレベルが決まれば、今の自分の立ち位置との「差」がはっきりします。どこまで学習が進んでいるのか、それは学校の進度で解決できるのか、難易度はクリアできるのか、自分の得意不得意と受験科目の整合性は・・・ さまざまなことがこのステップ1で確認できます。
ステップ2 入試を分析する
大学入試の問題は学校ごとにまったく違います。マークが中心、記述が中心といった形式だけでなく、思考力・判断力を問う問題が多い、一問一答式の問題が多いなどとその内容も千差万別です。ですから、志望校が決まったら、先ずはざっとその入試問題を見てみましょう。また、入試のプロである塾や予備校の先生に意見を求めましょう。敵を知らなければここからの学習の内容を決めることは出来ません。
ステップ3/4 現状を分析し得点戦略を描く
今の自分をしっかりと分析しましょう。理科や社会は学校の学習はどこまで進んでいるのか。そのペースで行くと単元の学習がおわるのはいつになるのか。もしも学校の進度が遅いようなら、自分でインプットの学習を前に進めるか、塾や予備校で学習をしていく必要がでてきます。また、自分のレベルと志望校の入試のレベルの「差」をしっかりと意識しましょう。その「差」を埋めることが受験勉強です。
ステップ5 学習を計画する
正直、ここまでのことを自分でやるのはなかなか難しいでしょう。できれば、大学入試に精通した塾や予備校の先生と相談しながら、ここまでの流れをもとに入試までの学習プランニングを立てましょう。具体的にどんな参考書、問題集を、いつまでにどうやってやっていくのか。細かく、具体的な計画が必要です。
そして、後はそれをコツコツとやっていくことです!!