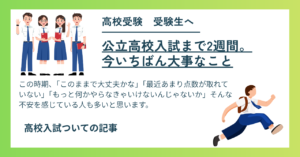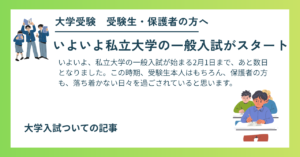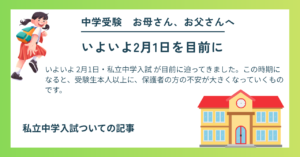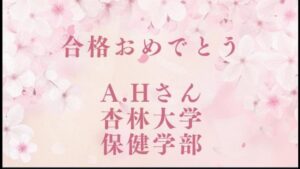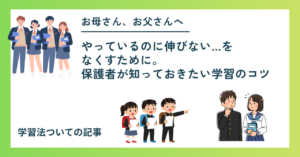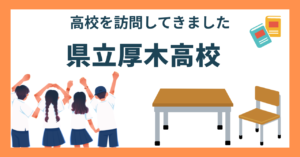古文が苦手でも大丈夫!短期間で力を伸ばす学習法
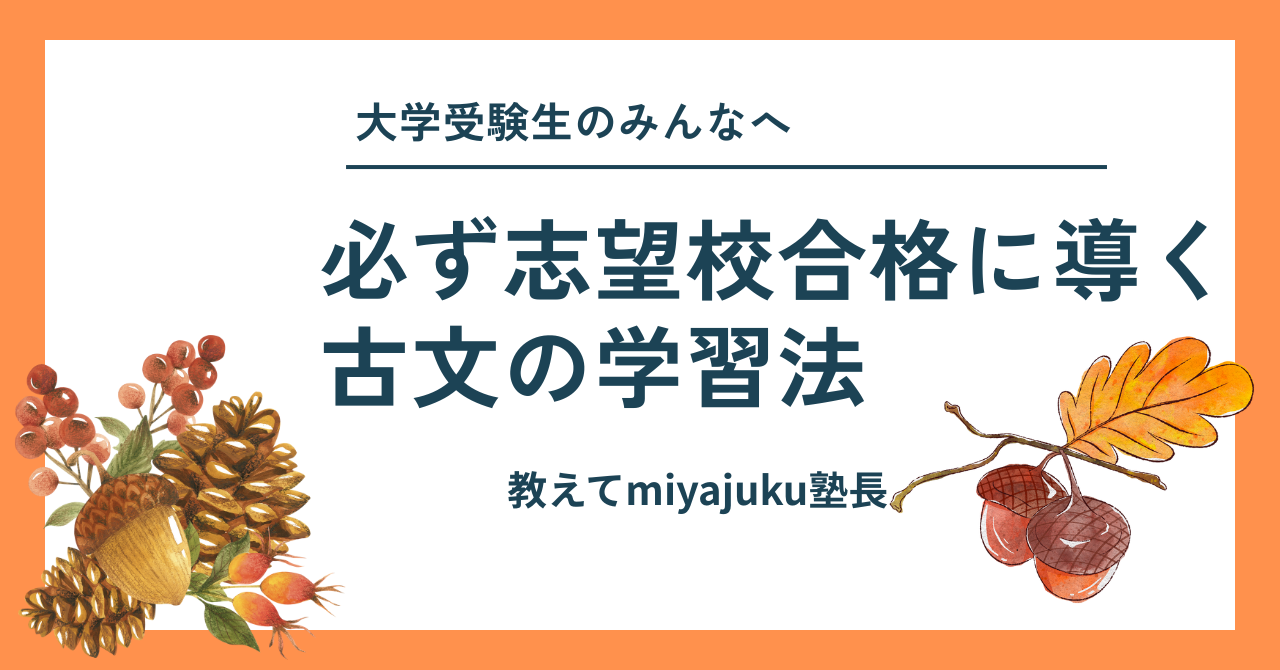
今日は「古文が苦手でどうしたらいいかわからない」という高校生に向けて、古文の勉強法についてお話しします。
👉 この記事は、受験生だけでなく「高1・高2のうちに古文を仕上げたい」という人にも役立ちます。

古文は「短期間で伸ばせる」教科
「古文があるから文系は避けようかな」と考えている人もいるかもしれません。でも実は古文は、正しいやり方で学べば短期間で力をつけられる科目なんです。
現代文や英語と同じように「言葉」を扱う教科ですが、必要な知識量は圧倒的に少なめ。だからこそ、やり方次第で一気に得点源にできます。
学習の3本柱:語彙・文法・読解
古文に必要なのは 語彙力・文法力・読解力 の3つです。順番に整理していきましょう。
1. 語彙(古文単語)
古文単語はおよそ300語程度。英語に比べたらずっと少ないですね。
例えば1日30語覚えれば、10日で1周できます。無理でも1か月あれば十分。
使う単語帳は『古文単語315』『古文単語330』など何でも構いません。大切なのは、現代語と意味が異なる語を重点的に覚えることです。
2. 文法
学校で習ったテキストや「古典文法演習ドリル」「古典文法10題ドリル」など、手元の教材で十分。
細かい知識にこだわるよりも、まずは文を分解できることが重要です。
- 文節に切れる
- 品詞を見分けられる(動詞・助動詞・助詞など)
この力がつくと、文章が一気に読みやすくなります。
3. 読解
演習は過去問にすぐ飛びつくのではなく、解説が丁寧な問題集を選ぶことをおすすめします。
例:
- 『ポラリス古文 基礎編』
- 『有名私大古文演習』(河合出版)
- 『古文上達 基礎編(45題)』(Z会)
ポイントは、現代語訳を自分で書いてみること。
2〜3行ずつでも構いません。訳を書き、解説と照らし合わせて正しく読めているかを確認します。
特に最初は「説話的な文章」や「有名どころ(平家物語など)」から入ると良いでしょう。逆に、人物関係が複雑なお姫様ものは後回しで大丈夫です。
実践プラン
- 1日1問を現代語訳してみる
- 週に5問、1か月で20問程度→ これだけでも古文の感覚が大きく変わります。
さらに、読むときは必ず「主語は誰か」を意識してください。古文は主語が省略されがちなので、敬語表現や人間関係から主体を見抜く練習が大切です。
過去問はいつから?
共通テストや難関私大の古文は、文章がややこしく主語もわかりにくいものが多いので、直前期からで十分です。まずは解説付きの教材で力をつけましょう。
参考書リスト(おすすめ教材)
古文単語
- 『古文単語315』(桐原書店)
- 『マドンナ古文単語230』(学研)
- 『古文単語330』(旺文社)
古典文法
- 『古典文法演習ドリル』(桐原書店)
- 『古典文法 基礎ドリル10題』(Z会)
- 学校で配布された教科書や文法書を繰り返すのも効果的
読解・問題集
- 『ポラリス古文 基礎編』(KADOKAWA)
- 『有名私大古文演習』(河合出版)
- 『古文上達 基礎編(45題)』(Z会)
勉強スケジュール例(2か月プラン)
1か月目(基礎固め)
- 毎日:古文単語30語(300語を1周)
- 週3回:文法ドリル1題(計12題で1冊終了)
- 週2回:読解問題集で1問(現代語訳を書いて確認)
👉 これで語彙と文法の基礎が固まり、古文の文章に慣れていく
2か月目(実践強化)
- 毎日:古文単語20語(2周目に入る)
- 週2回:文法の弱点復習(苦手な助動詞など重点)
- 週3回:読解問題集で1問(1日30分で現代語訳→解説確認)
- 月末:学校の模試や小テストでアウトプット確認
👉 2か月で「語彙2〜3周」「文法1冊」「読解20〜30問」が仕上がれば、古文の得点力は一気に安定します。
まとめ
- 古文単語は300語、毎日コツコツ繰り返す
- 文法は文を分解できるレベルまで固める
- 読解は解説の丁寧な問題集で現代語訳を自分で書く
- 説話や有名どころから始める
- 過去問は冬以降でOK
古文は「やれば伸びる科目」です。入試本番で大きな得点源にできるので、ぜひ諦めずに取り組んでください!