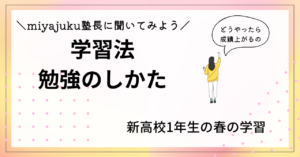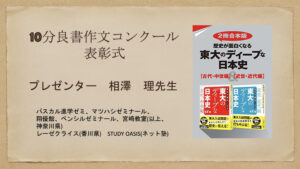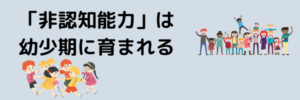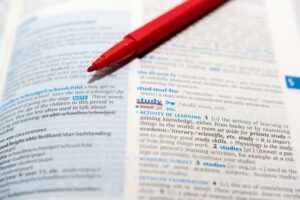デジタルデバイスを学習に使うべきかどうか

先週の土曜日から保護者の方との面談が続いています。1週間で30人ほどの方と新学期スタートの中での様々な学習のお悩みにできうるかぎりおこたえしています。そんな中、デジタルデバイスを使うべきか、といったお話をいくつかいただきました。以下はそのヒントになればと思っての記事です。
わたしの上の孫も年中さんになりました。昨年から「スマイルゼミ」をはじめていて、毎日必ず取り組んでいます。
何をやったかがわたしのスマホに送られてくるのですが、年中さんになって「お話し」の読み聞かせがあり、最後にそのお話についての簡単な質問に音声で答えたものも送られてきます。
いまは「浦島太郎」を読んでいるらしく、その最後の質問の答えが送られてきます。簡単なやり取りですが、乙姫様と別れたときの浦島太郎の気持ちを「寂しい」と理解しているのがわかります。質問は「登場人物を見分けることが出来た」「物語の流れを理解できた」「登場人物の気持ちを理解できた」「出来事の結果を理解できた」などと多岐にわたっています。
デジタルデバイスをどう学習の中で使うのか。この孫の取り組みがひとつのヒントだと思っています。
① 指導者がいなくてもひとつの流れの中で子どもが学習できる。
② インプットとアウトプットをセットにして学習できる。
③ 短時間で効果的な学習が出来る。
④ 音声や映像を合わせた学習スタイルがとれる。
⑤ 継続的な学習をデバイスが支援する仕組みがある。
同時にこうした学習ツールは使いようです。「使わない」という選択肢は今の時代にはありません。ですから「使う」のであれば、「どう使うか」をしっかりと考えて使うべきです。いずれにしても、こちらが使われないように使えば最強の学習パートナーになります。